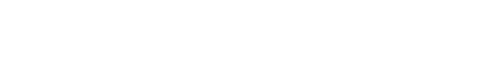鍼治療はなぜ効くのか?
― 現代医学的に解明されてきた作用メカニズム ―
かつては「東洋医学の不思議な力」とされてきた鍼治療ですが、近年の医学研究により、その効果の仕組みが科学的に解明されつつあります。
ここでは、鍼治療が身体にどのように作用するのか、現代医学の視点からご紹介します。
① 神経を通じて脳や内臓に作用する
鍼を皮膚や筋肉に刺すことで、末梢神経(感覚神経)に微細な刺激が加わります。
この刺激は、脊髄を通って中枢神経(脳)に伝わり、以下のような反応を引き起こします:
- 脳内ホルモンの分泌促進(エンドルフィン・セロトニンなど)
- 自律神経の調整(交感神経と副交感神経のバランス)
- 内臓の機能調整(胃腸・心臓・肝臓など)
このように、鍼刺激は全身の調整役として脳や内臓に働きかけるのです。
② 血流改善・局所炎症の軽減
鍼刺激により、筋肉や皮膚の局所において、
- 毛細血管の拡張
- 筋肉の緊張の緩和
- 発痛物質(ブラジキニンやヒスタミンなど)の抑制
などが起こります。これにより、肩こりや腰痛などの痛みが軽減し、血行が良くなるとされています。
実際、MRIやサーモグラフィーなどでも、鍼治療後に血流が改善している様子が可視化されています。
③ 内因性鎮痛メカニズム(脳内モルヒネ)
鍼を打つことで、脳内に「エンドルフィン」や「エンケファリン」など、体内で作られる天然の鎮痛物質が分泌されます。
これらは「内因性オピオイド」と呼ばれ、鎮痛剤と似た作用を持つため、薬を使わずに痛みを緩和できるのです。
④ 自律神経とホルモンバランスを整える
ストレスや不眠、生理不順などは、自律神経やホルモンバランスの乱れが原因となることが多くあります。
鍼刺激は、視床下部―下垂体―副腎系(HPA軸)など、ホルモン分泌をコントロールする中枢にも作用するため、心身のバランスを整える作用が期待されています。
⑤ 脳の働きを正常化(fMRI研究)
最新のfMRI(機能的MRI)研究では、鍼刺激によって脳の特定部位の血流が変化することが確認されています。
たとえば、不安やストレスを感じると活性化する「扁桃体」の活動が、鍼治療によって鎮静化されることが報告されています。
まとめ
| 鍼治療の作用 | 医学的な説明 |
|---|---|
| 痛みの緩和 | 内因性オピオイドの分泌による鎮痛作用 |
| 血流改善 | 局所の血管拡張・筋緊張の緩和 |
| 自律神経調整 | 副交感神経優位へ導く作用 |
| ホルモン調整 | HPA軸への作用、女性ホルモンのバランス調整など |
| 精神安定 | セロトニンやエンドルフィン分泌、扁桃体の鎮静化 |