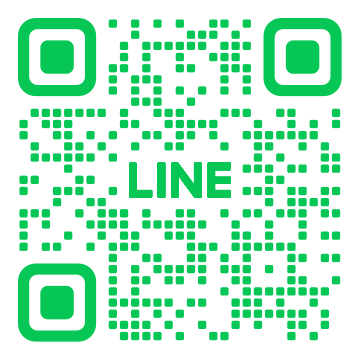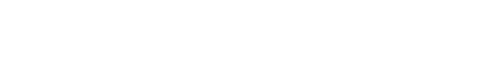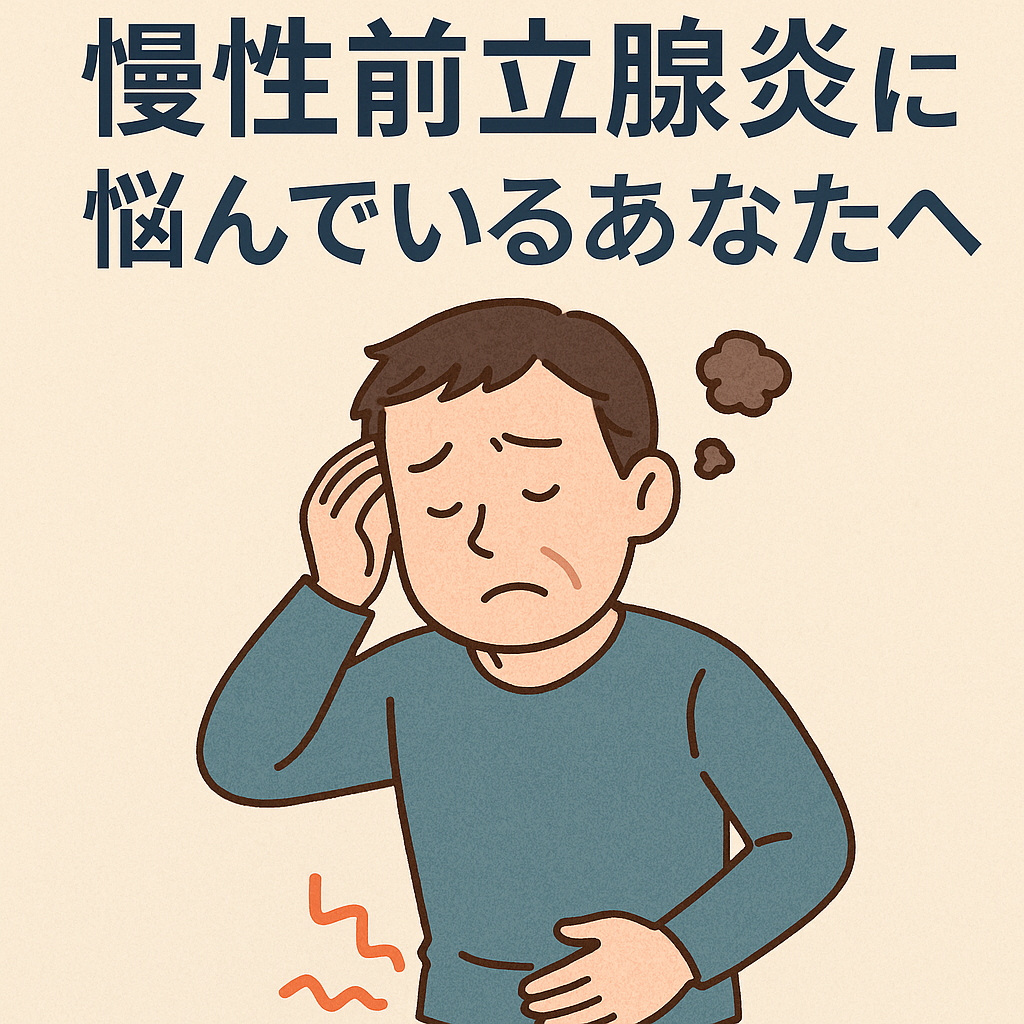「トイレの後に残尿感が続く」「会陰部や下腹部に鈍い痛みが消えない」「泌尿器科で薬を処方されても改善しない」
こうした悩みを抱えている男性は少なくありません。その代表的な症状のひとつが慢性前立腺炎です。
慢性前立腺炎は、数か月から数年にわたり症状が続くことがあり、生活の質を大きく下げてしまう病気です。特に30代から50代の働き盛りの男性に多く見られ、デスクワークやストレスの多い生活習慣とも関係しています。病院での治療を受けてもなかなか改善がみられず、途方に暮れて当院へ相談される方も少なくありません。
本記事では、慢性前立腺炎の原因や症状、そして薬以外の選択肢として注目されている鍼灸治療の可能性について解説いたします。
慢性前立腺炎とは?
慢性前立腺炎とは、3か月以上にわたって前立腺や骨盤周囲に痛みや違和感が続く状態を指します。大きく分けると以下の種類があります。
- 慢性細菌性前立腺炎:細菌感染によって炎症が続くタイプ。抗菌薬が有効な場合があります。
- 慢性非細菌性前立腺炎(慢性骨盤痛症候群):細菌は検出されないものの、痛みや不快感が続くタイプ。実際にはこちらが圧倒的に多いとされています。
主な症状
- 会陰部(肛門と陰嚢の間)の痛みや違和感
- 下腹部・腰・太ももの付け根の重だるさ
- 排尿時の不快感、残尿感
- 性生活への影響(射精時の痛み、勃起不全など)
- 精神的な落ち込み、不安感
このように症状は多岐にわたり、日常生活や仕事の集中力にも影響を与えます。
なぜ慢性前立腺炎は治りにくいのか?
泌尿器科で薬を服用しても改善しにくいのには理由があります。
- 骨盤内の血流障害(うっ血)
長時間の座位や運動不足により、前立腺や骨盤周囲の血流が滞ることで炎症が長引くケースがあります。 - 骨盤底筋の過緊張
デスクワークや自転車の習慣で骨盤底筋が硬直し、慢性的な圧迫や炎症を引き起こします。 - 自律神経の乱れ
交感神経が過剰に働くと、痛みの感受性が高まり、排尿機能も不安定になります。 - ストレスや心理的要因
痛みそのものがストレスになり、不安や抑うつがさらに症状を悪化させる「悪循環」に陥ることも。
つまり慢性前立腺炎は、単に「前立腺の病気」というより、骨盤全体や自律神経、生活習慣と深く関わる症候群といえます。
鍼灸治療で期待できる改善
鍼灸は、血流改善や筋肉の緊張緩和、自律神経の調整を得意としています。慢性前立腺炎に対しては、以下のような作用が期待できます。
1. 骨盤内の血流を促す
鍼やお灸を下腹部や腰、足に行うことで血流を促進し、うっ血を解消します。血流が改善すると炎症の鎮静や組織の修復がスムーズになります。
2. 骨盤底筋の緊張を和らげる
経穴(ツボ)を刺激することで骨盤底筋や周囲の筋肉のこわばりを緩め、会陰部の圧迫感や鈍痛を軽減します。
3. 自律神経のバランス調整
鍼灸は交感神経の過緊張を抑え、副交感神経を優位にする作用があります。これにより排尿機能が安定し、痛みの感受性も低下します。
4. 心身のリラックス
施術中の心地よい刺激や温熱効果によってリラックスが得られ、慢性症状を悪化させるストレス要因も軽減します。
実際の患者さんのケース
30代男性。半年以上、会陰部の鈍痛と排尿時の不快感が続き、泌尿器科では「慢性前立腺炎」と診断されました。抗菌薬や鎮痛薬を試したものの効果は乏しく、日常生活にも支障をきたす状態に。
当院で週1回の鍼灸施術を開始。腹部・腰・骨盤周囲の血流を改善するツボを中心にアプローチしたところ、3か月後には痛みが半減し、排尿のスッキリ感が戻ったと喜ばれました。
もちろん効果の出方には個人差がありますが、薬で改善が難しいケースにおいて鍼灸が有効に働くことがあります。
まとめ
慢性前立腺炎は薬だけで改善しにくく、長期的に悩まされる方が多い症状です。その背景には骨盤内の血流障害、筋肉の緊張、自律神経の乱れ、ストレスなど多くの要因が関与しています。
鍼灸治療は、
- 骨盤内の血流改善
- 骨盤底筋の緊張緩和
- 自律神経の調整
- 心身のリフレッシュ
といった多角的なアプローチが可能です。
「慢性前立腺炎でつらい毎日を送っている方に、もう一つの改善方法として鍼灸治療を知っていただきたい」
これが私たちの願いです。
👉ご相談、施術のご予約はLINEからお気軽に➡https://lin.ee/5X2dY7a