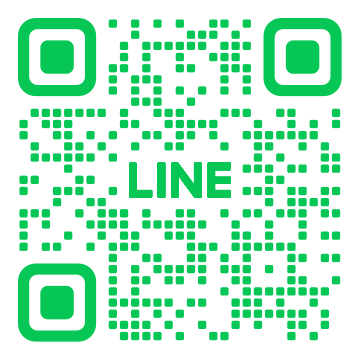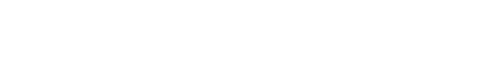■ 朝起きてもスッキリしない…それ、“冷え疲れ”かもしれません
「たっぷり寝たはずなのに、朝から体が重い」
「休んでも疲れが取れない」
そんな声が、秋から冬にかけて特に増えてきます。
このような“だるさ”や“疲労感”の背景には、**自律神経の乱れによる「冷え疲れ」**が隠れていることがあります。
気温の低下や気圧変化、日照時間の短さが重なるこの季節は、体がストレスを受けやすく、交感神経が過剰に働きやすい時期です。
■ 自律神経と「冷え」の深い関係
自律神経は、私たちの体温調整・血流・内臓の働きなどをコントロールしています。
外気温が下がると、体は体温を保つために血管を収縮させますが、これを調整しているのが自律神経です。
しかし、冷えやストレスが続くと次第に調整機能が乱れ、
- 血流が滞る
- 手足が冷える
- 筋肉がこわばる
- 代謝が落ちる
といった症状が現れます。
この状態が続くと、**「冷えたまま緊張が抜けない=冷え疲れ」**の状態になります。
■ なぜ秋冬に「冷え疲れ」が起こりやすいのか?
① 気温差によるストレス
秋口から冬にかけては、朝晩と日中の気温差が10℃以上になることもあります。
この気温変化に対応するため、自律神経はフル稼働。
結果、交感神経が優位になり続け、夜になってもリラックスモード(副交感神経)に切り替えられなくなります。
② 日照時間の減少
日照時間が短くなると、脳内のセロトニン(幸福ホルモン)が減少し、
心身のリズムが乱れやすくなります。
睡眠を促すメラトニンの分泌も狂いやすく、結果的に「寝ても疲れが取れない」状態に。
③ 気圧変化と体調不良
秋冬は低気圧が多く、気圧の変化が自律神経に刺激を与えます。
頭痛や肩こり、めまい、倦怠感なども同時に起こりやすくなるのです。
これが「気象病」や「天気痛」と呼ばれる症状の正体です。
■ 鍼灸で整える「自律神経」と「冷え疲れ」
にしむら鍼灸治療院では、こうした自律神経の乱れに伴う慢性的な疲れ・冷えに対して、
鍼灸によるアプローチを行っています。
● 鍼灸の作用メカニズム
鍼やお灸を使って、ツボや筋肉を刺激することで――
- 自律神経のバランスを調整(交感神経→副交感神経へ)
- 血流改善による体温上昇
- 内臓や脳への血流促進による代謝回復
- ストレスホルモン(コルチゾール)の抑制
といった効果が科学的にも報告されています。
実際に治療を受けた患者さんの中には、
「夜ぐっすり眠れるようになった」
「朝スッと起きられるようになった」
という声も多く聞かれます。
■ 「冷え疲れ」を悪化させる生活習慣
知らず知らずのうちに自律神経を乱す行動もあります。
当院では、以下のような点を意識して生活指導を行っています。
✖ スマホを寝る直前まで見る
ブルーライトは交感神経を刺激し、脳を「昼」と勘違いさせます。
✖ 熱いお風呂で長時間入浴
一時的に温まっても、のぼせや血圧上昇で自律神経を乱す原因に。
✖ 冷たい飲み物・甘い物の摂りすぎ
胃腸が冷えると内臓の血流が低下し、自律神経の働きも鈍ります。
■ 自律神経を整えるセルフケア
自宅でできる簡単なセルフケアも、毎日の積み重ねで効果が出ます。
🌿 朝:首・肩を温めながら深呼吸
交感神経が優位な朝に、呼吸と温熱でリラックスモードに。
🧘♀️ 夜:お腹まわりを温めて“副交感神経スイッチ”をON
寝る前に腹巻きやお灸で丹田(へその下)を温めましょう。
冷えが和らぐと、自然と眠りの質が上がります。
☀️ できるだけ朝日を浴びる
起きてすぐカーテンを開けて太陽光を浴びると、体内時計がリセットされ、セロトニンも活性化します。
■ 鍼灸治療で“体のリズム”を取り戻す
自律神経の乱れによる不調は、薬ではコントロールしにくい場合があります。
そのため、体の内側からリズムを整える鍼灸が注目されています。
にしむら鍼灸治療院では、
- 手足の冷え
- 寝ても疲れが取れない
- 頭の重だるさ
- 胃の不快感や食欲不振
- イライラや不安感
など、“はっきりした原因が分からない不調”にも丁寧に対応しています。
体全体のバランスを見ながら、「副交感神経を働かせる」施術を中心に行うことで、
自然と眠り・血流・消化・心の落ち着きが戻ってくるケースが多いです。
■ まとめ:「疲れが取れない」は体からのサイン
「朝起きても疲れが取れない」というのは、単なる“年齢”や“気のせい”ではなく、
自律神経がオーバーワークを起こしているサインです。
冷え・気圧・日照時間の変化に負けない体づくりのために、
鍼灸で“リズムの再起動”をしてみませんか?
にしむら鍼灸治療院では、あなたの体の状態に合わせた施術で、
心と体を同時に整えるサポートを行っています。
ご相談、施術のご予約はLINEからお気軽に➡https://lin.ee/5X2dY7a